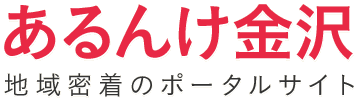楽しむ・学ぶ
-
宇多須神社
養老2年(718)卯辰村字一本松に卯辰治田多聞天社として創建され後に今後に遷座した。 俗に毘沙門さんと呼ばれている。 慶長4年藩祖前田利家公が薨去し現神社境内地に鬼門鎮護の神社として社殿を建てて利家公の神霊を祀り卯辰八幡宮と称した。 明治6年(1873)に利家公の神霊は現在の尾山町に社殿を造営し尾山神社としてお祀りされたが、卯辰八幡宮は旧社殿を改修・造営して従前よりの本社の神霊を遷座して宇多須神社と改称した。 平成16年(2004)尾山神社より前田利家公の御分霊を遷座し合祀祭を執り行った。
-
田井菅原神社
菅原道真公から授けられた自画像を大切に守り伝えている神社で、境内地には前田斉泰公より拝領した大国主命が祀られていたり、松尾芭蕉の句碑があります。 また、加賀藩主献上鏡餅は平成9年より古例に則りお正月に奉納しています。
-
うみっこらんど七塚 キャンプ場
「うみっこらんど七塚 キャンプ場」は、キャンプ場とバーベキュー場があり、施設内に”海と渚の博物館”を併設しています。 美しい夕焼けを望む場内は、緑に囲まれ、きれいに整備が行き届いた炊事場や管理棟があり、キャンプ初心者でも快適に過ごせます。 また、白尾海水浴場がすぐそばにあり、釣りや海水浴を満喫したあとは、日本海に沈む夕日を眺めながら、バーベキューを堪能することもできます。今年の夏は、「うみっこ」でキマリ! キャンプ初心者向けの、お得なセット料金もあります。詳しくは、うみっこらんど七塚のホームページをご覧下さい。 ・テントサイト オートサイト(21区画)、フリーサイト(13張) ・BBQ 6卓 10日前までにご予約をお願いします。 基本料金 ・オートサイト 1区画/1泊(5人まで)5,000円 ・フリーサイト 1張/1泊(5人まで)2,000円 ・バーベキュー 1卓1,000円、1人(小学生以上)100円 1卓の定員10人 詳しいことは、HPまたはお問い合わせください。
-
明泉山 髙安軒
明泉山 髙安軒は、野々市市にある曹洞宗の寺院のひとつです。 拝観は境内(外)のみ可能で、無料となっております。 詳しくはホームページをご覧ください。
-
うみっこらんど七塚・海と渚の博物館
「うみっこらんど七塚・海と渚の博物館」は、人と海との関わりとくらしをテーマに、能登半島の海の民俗資料を今に伝える自然体感型の博物館。 船をイメージした内井昭蔵氏設計の優美な館内の展示場には、昭和初期から30年代後半にかけて、かほく市海岸一帯や能登半島の漁村に使われていた、数多くの貴重な漁具類や郷土資料を展示してあります。「櫓こぎ」や「たらい漁」などの疑似体験コーナーやスタンプラリー、クイズコーナーもあり、楽しみながら海と人との暮らしを学べます。 体験メニュー ・貝殻アート体験(10日前までの予約制)1回200円 ・貝殻アート体験の団体利用も受け付けていますので、事前にお問い合わせください。 入館料 大人200円 高校生以下100円 乳児無料 団体料金(20人以上)大人150円 高校生以下50円 プレミアムパスポートに記載の家族は無料で入館できます。
-
石川県西田幾多郎記念哲学館
石川県西田幾多郎記念哲学館は、日本を代表する哲学者・西田幾多郎の人物記念館であると同時に、哲学をテーマにした「哲学の博物館」でもあります。建築家・安藤忠雄氏が設計した建物の中で自ら「迷い、考えること」をお楽しみください。 哲学館では展示のほか、さまざまな講演会・講座を行っております。またホワイエ・展望ラウンジを展示会場としてご利用いただくことも可能です。詳しくは、哲学館ホームページをご参照ください。
-
法隆山 真行寺
法隆山 真行寺は、金沢市にある曹洞宗の寺院のひとつです。 拝観は本堂など伽藍内可能で、無料となっております。 詳しくはホームページをご覧ください。
-
金沢湯涌江戸村
金沢を中心とする加賀前田藩は、江戸時代日本最大の藩でした。加賀・能登・越中(石川・富山両県)にひろがった加賀百万石の文化や生活は、江戸(東京)とならんで、この時代を代表するものです。城下町金沢には武士と町人が住み、それを取り巻く広い農村には農民が住んでいました。江戸時代は身分によって住む家の造りが異なり、武士の家は門や塀で囲まれた屋敷構えをとり、町人の家は通りに面して直接建つ町家で、農民の家は茅葺きの農家でした。 金沢湯涌江戸村は、江戸時代のこれらの民家を移築した施設です。武士の家は足軽住宅の永井家。町家は大商家の山川家と、簡素な小型の商家の松下家で、これら城下町金沢の家はどれも板葺き石置き屋根です。能登の農家は古い形を残す平家と、肝煎(村長)クラスの野本家、加賀の農家はこの湯涌地区にあった高田家と、紙漉き農家の園田家で、茅葺き農家は合計4軒。ほかに街道の宿場町で、大名が泊まった本陣の石倉家もあります。
-
尾﨑神社(旧金沢東照宮)
尾﨑神社は、もともとは金沢城内北ノ丸にあり、「金沢東照宮」・「御宮」と呼ばれた由緒ある神社です。 創建は寛永20年(1643)と古く、4代藩主前田光高が幕府から格別の許しを得て、上野寛永寺から勧請し造営され、明治11年(1878)に城外の現在地に移された。 本殿に残る飾金具や彩色は、創建当初の状態をよく残していることから、初期金沢城の貴重な建築物の遺構とされている。
-
尾山神社
加賀藩祖前田利家公と御正室お松の方を神様とする神社。 1599年利家公薨去後、2代目藩主利長公は利家公を神として祀ろうとしたが外様大名として徳川家にはばかり 八幡神を祀る卯辰八幡宮を卯辰山に建立し、利家公の御霊を合祀した。廃藩置県後の明治6年、旧加賀藩士らは利家公の功績を不朽に伝えんと旧金谷御殿跡地である現在の社地に尾山神社として遷座した。 境内に建つ神門は明治8年の建築で国重要文化財指定。和漢洋の様式が混用した現在では貴重な擬洋風建築物である。 三層構造の第三層は四面五彩のギヤマン張りで日没後には御神灯が灯される。 また、境内の庭園は別名「楽器の庭」と呼ばれ、園内の島や池が古代舞楽の楽器を模した池泉回遊式の庭園で県指定名勝。 金沢城側に建つ東神門は旧金沢城の二の丸の唐門を移築したもの。火災でほとんどが焼失した金沢城の中で当時の桃山風御殿建築を伝える貴重な建造物。